1983年熊本県水俣生まれ。
中学卒業後に水俣を離れるが、書道の恩師・溝口秋生さんの水俣病裁判と出会い、2007年水俣に戻る。
2008年より、水俣病センター相思社職員。水俣病患者相談窓口や相思社の運営する水俣病歴史考証館の解説、機関紙「ごんずい」の編集などを担当。
単著に患者と向き合う日々の思いをつづった『みな、やっとの思いで坂をのぼる 水俣病患者相談のいま』(ころから/2018年)がある。
人や場所の記憶を受け取り伝える方法はひとつではないし、
特定の誰かが伝えていく必要もない。
受け取ったその人が自身の内面の世界に波紋を広げていった先に「継承」という行為が現れてくるのではないでしょうか。
これまで大きな主語で語ってこられた数々のこと、小さく小さく、個々の物語にしたときに見えてくる何かがあるのかもしれません。
長島から生まれる様々な対話によって、自分と異なる他者に触れる。
まだ知らない私自身を発見する。尊重という行為を知る。
そうして、新しい世界へ橋が架かっていくと私たちは信じています。
大切なことは、目に見えるとは限らないし、
聴こえてくるものでもないかもしれない。
はたまた、自分の輪郭さえ失うほどの闇の中で、
見つかるかもしれない。
国立療養所 長島愛生園は2030年に100周年を迎えます。
幾重にも重なった歴史を自身の身体を使って紐解き、
足元深く、内面にある新しい感覚を呼び覚ます。
ひらかれた長島から心に橋を架け渡します。

(一財)水俣病センター相思社
永野三智
NAGANO Michi

dialogue

喫茶さざなみハウス
鑓屋翔子
YARIYA Syoko

岡山大学文学部准教授
松村圭一郎
MATSUMURA Keiichiro
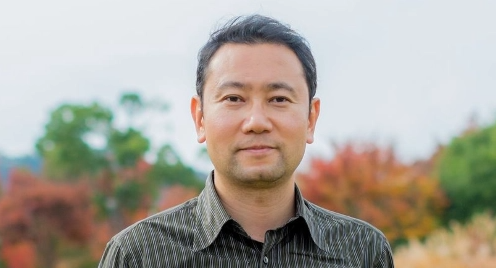
水俣病センター相思社
永野三智
NAGANO Michi

喫茶さざなみハウス
鑓屋翔子
YARIYA Shoko

1988年大阪市生まれ岡山育ち。
大学を卒業してUターン、地方で暮らすことを模索し、働きながら近所の空き家を改修したり、中間支援のNPOで県内の地域に出向いたり、ゲストハウス複合施設での勤務を経て、2019年7月より長島愛生園内で喫茶さざなみハウスをスタート。
喫茶営業のかたわらで、入所者の方の暮らしや療養所の歴史を記録し、島の外にいる人たちに向けて発信しています。
岡山大学文学部准教授
松村 圭一郎
MATSUMURA Keiichiro

1975年熊本生まれ。
岡山大学文学部准教授。
専門は文化人類学。
所有と分配、海外出稼ぎ、市場と国家の関係などについて研究。
著書に『うしろめたさの人類学』(ミシマ社、第72回毎日出版文化賞特別賞)、
『はみだしの人類学』(NHK出版)、
『これからの大学』(春秋社)、
『くらしのアナキズム』(ミシマ社)など、
共編著に『文化人類学の思考法』(世界思想社)、『働くことの人類学』(黒鳥社)。
私のきっかけから
入っていける

松村
水俣もいろんな文化が芽生えているっていう点では共通してるかなって思うんですけど、石牟礼道子さんの小説だけじゃなくて、先ほど出たユージン・スミスの写真も土本監督のドキュメンタリーも。あとお能とか、音楽フェスとかもやられてましたかね。
永野
そうですね。『渋さ知らズ』とかね。
松村
その辺の動きって勉強するだけじゃない、文化によって発信してきたり、それに惹きつけられていろんな人が関わっていく流れというのは、水俣でも進行中ですか?
永野
そうだと思います。
でもね、一方でうちの職員はね、水俣に来て「石牟礼マジックが解けた」って。
「なんの魅力も感じなくなった」って。
松村
えー、どういうこと?
永野
おもしろいなと思って。水俣に来て10年、プライベートでも仕事でも水俣病を考えてるんですよ。
『苦海浄土』が水俣に来たきっかけだったのに、石牟礼さんのこと、もうけちょんけちょんですよ。
「なんなんだろうね、あの人」っていう感じ。
松村
それ、おもしろいですね。
永野
でも、確実に考えるきっかけにはなってます。
そういう人を生み出してるっていう意味では。
長島も水俣もそうだと思うんですけど、いろんなジャンルで発信を続けていて、どこの切り口からでも入っていけるっていうのがとっても魅力かなと思います。
松村
先ほどの石牟礼マジックみたいなのって、多分それもひとつの「自分の水俣像」みたいなものが自分の中に芽生えてくるっていう話なんですよね。
永野
そうだと思います。
地域の人たちと触れ合ってみて、「石牟礼はいかんもう」「いかんもんなぁ。あらぁもう旦那が可哀想ばい」みたいな話を聞いたり。
実際暮らしてみて、「そんなもんじゃなかった」とか聞くと、「そうなん?もうちょっと詳しく聞かせて」と、その変化にワクワクします。

松村
いろんな発信をする人を輩出しているけど、そこに惹きつけられて来る人が自分なりの水俣像とか、自分のリアルな水俣に出合っていくっていうのは。
永野
そうなった時点でもう当事者だと思うんですよね。
松村
すごいですよね。
永野
自分を生きるというか、そこで自分を生かしていくとか、そういう人たちがまた周りを生かしていくわけですよね。
そういうスパイラルってすごくおもしろいですよね。
松村
それはまさに今日のタイトルの「私を生きる」ってところになんか。
永野
がんばって寄せていこうと思って。
松村
冒頭で永野さんに出していただいた継承問題も各々がそれぞれのかたちで関わって、自分なりの語り口を獲得していくみたいな。
それでいいんですね。
永野
そうなんですよ。
それで既に継承はできていて、終わってるんですよね。
そこからまた、水俣病に関わり始めて1年目の私と、14年15年目の私は語りがまったく違うと思うんです。
違っていいんですよ。
その変化を記録していく。
今の自分が一番生き生きするなと思うのが、「記憶を記録する」っていうことなんです。
最近ですね、相思社の庭とか道を歩いてる時に、「あっ、これは食べられる。どうやって食べよう」ってことばかり気になって。
そういうのは、全部患者の方から教わったんですよね。既に私の意識に根付いて継承されているというか。
私も誰かに「これうまかったいな」って伝えることで継承されていく。
そんな感じでいいんじゃないですかね、継承って。

【つづきます】







