1983年熊本県水俣生まれ。
中学卒業後に水俣を離れるが、書道の恩師・溝口秋生さんの水俣病裁判と出会い、2007年水俣に戻る。
2008年より、水俣病センター相思社職員。水俣病患者相談窓口や相思社の運営する水俣病歴史考証館の解説、機関紙「ごんずい」の編集などを担当。
単著に患者と向き合う日々の思いをつづった『みな、やっとの思いで坂をのぼる 水俣病患者相談のいま』(ころから/2018年)がある。
人や場所の記憶を受け取り伝える方法はひとつではないし、
特定の誰かが伝えていく必要もない。
受け取ったその人が自身の内面の世界に波紋を広げていった先に「継承」という行為が現れてくるのではないでしょうか。
これまで大きな主語で語ってこられた数々のこと、小さく小さく、個々の物語にしたときに見えてくる何かがあるのかもしれません。
長島から生まれる様々な対話によって、自分と異なる他者に触れる。
まだ知らない私自身を発見する。尊重という行為を知る。
そうして、新しい世界へ橋が架かっていくと私たちは信じています。
大切なことは、目に見えるとは限らないし、
聴こえてくるものでもないかもしれない。
はたまた、自分の輪郭さえ失うほどの闇の中で、
見つかるかもしれない。
国立療養所 長島愛生園は2030年に100周年を迎えます。
幾重にも重なった歴史を自身の身体を使って紐解き、
足元深く、内面にある新しい感覚を呼び覚ます。
ひらかれた長島から心に橋を架け渡します。

(一財)水俣病センター相思社
永野三智
NAGANO Michi

dialogue

喫茶さざなみハウス
鑓屋翔子
YARIYA Syoko

岡山大学文学部准教授
松村圭一郎
MATSUMURA Keiichiro
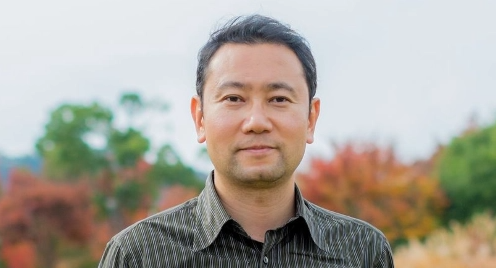
水俣病センター相思社
永野三智
NAGANO Michi

喫茶さざなみハウス
鑓屋翔子
YARIYA Shoko

1988年大阪市生まれ岡山育ち。
大学を卒業してUターン、地方で暮らすことを模索し、働きながら近所の空き家を改修したり、中間支援のNPOで県内の地域に出向いたり、ゲストハウス複合施設での勤務を経て、2019年7月より長島愛生園内で喫茶さざなみハウスをスタート。
喫茶営業のかたわらで、入所者の方の暮らしや療養所の歴史を記録し、島の外にいる人たちに向けて発信しています。
岡山大学文学部准教授
松村 圭一郎
MATSUMURA Keiichiro

1975年熊本生まれ。
岡山大学文学部准教授。
専門は文化人類学。
所有と分配、海外出稼ぎ、市場と国家の関係などについて研究。
著書に『うしろめたさの人類学』(ミシマ社、第72回毎日出版文化賞特別賞)、
『はみだしの人類学』(NHK出版)、
『これからの大学』(春秋社)、
『くらしのアナキズム』(ミシマ社)など、
共編著に『文化人類学の思考法』(世界思想社)、『働くことの人類学』(黒鳥社)。
私として生きられる場所

松村
永野さんのお話を聞いてたら、水俣にまた行きたくなりますよね。
私は熊本市で生まれ育って、熊本市の人間にとって水俣って、同じ熊本県でも遠いんですよね。 地理的にも心理的にも。
今は新幹線で簡単に行けるようになったけど、地理的には、むしろ鹿児島に近いぐらいの場所だし。
やっぱり水俣病事件という重い歴史を背負ってるみたいな感じがあって、むしろ関わりにくさがあったんです。
永野
ね。なんか重い歴史を背負わなきゃいけないってなってますよね。
不幸な顔しとかなきゃいけないみたいな。
松村
でも、永野さんの楽しそうな話を聞いてると、一緒に行ってビナ食べたいなとか。
永野
そうなんですよね。
やっぱり年がら年中、不幸な顔をしてたら生きていけないなって。
よく語ってくれる患者さんがいるんですけど、その人の20年前の語りを私は知らないんですよね。20年前は、「もう水俣ば変えんばいかん!日本ば変えんばいかん!私はこげん家族が殺されて、おら傷つけられて、大変な思いばしてきた!」っていう語りだったらしいんですよ。
でも今は「何で語ってるんですか?」って学生さんが真摯に聞くと、「あた(あなた)に、頼まれたけんたい」みたいな冗談で返して大笑いする。そこで冗談で返してたくましく生きていく。
もう辛い顔をずっとしてたらやっていけないみたいな。
その患者さんのそういう変化って「私を生きる」だと思うんですよね。
そんなふうにして私をどう生きてきたか、記憶の定点観察じゃないですけど、記録していきたいですよね? 鑓屋さん。

鑓屋
本当に。
永野
またなんか会いたいですね。
私、今回、長島に行く予定だったんですよ。
松村
そうなんですよ。
本来は長島でリアルにやる予定で。
永野
本当、次行きますけん!
鑓屋
ゆっくりしゃべりましょう。
永野
はい。
またぜひぜひ企画してください。
松村
最後に鑓屋さん、どうでした?
『内なる海、私を生きる。』っていうテーマで永野さんと話そうっていう企画でしたが、なんかよき先輩っていう感じがしますよね。
永野
そんな、先輩風吹かせてすみません。
松村
永野さんの境地に達したい、というところもあったんじゃないかなって思って。
鑓屋
本当にすごく軽やかで、永野さんがいる水俣の空気に触れたいって、単純にそう思える永野さんのキャラクターで。
私は何も知らない状態から少しずつハンセン病や長島のことを知って、いろんな人の様々な考えがあることを知って。
今自分がやってることって、すごく軽率なことだったりするんじゃないか。
そういう葛藤も大きかったりして、いつも揺られるんですけど。
打ち合わせで「生活の話をしよう」って言われた時に、やっぱり私は長島の人たちの生活に触れてるからこそ「こんなことやってみよう」とか、
「あんなこと聞いてみよう」とか、楽しくここで過ごせてるんだなって思って。
だから「これでいいんだ」って気持ちになれました。
今日話してみて、私もこの先どんな考え方になるかわからないけど、関わってくれるみなさんとそれぞれにとっての「私として生きられる場所」を続けていけばいいんだなって思えて。
相思社の縁側の暖かい日差しに終始癒されるような気分で。私もツワを剥きたいと思いました。
永野
ぜひ縁側でお話ししましょう。
松村
水俣病とかハンセン病って、もう100年近い大きな歴史のなかの出来事ですよね。
水俣にチッソができてもう100年以上経つし。
永野
そうですね。
来年2023年はね、漁師が初めてチッソを訴えて100年なんですよ。
これ私「やるぞ!」って思ってて。
松村
何かイベントをやるんですか?

永野
関東大震災の朝鮮人虐殺事件からも100年なんですよね。
そこにもつながるし、水俣単独でもガーッっていろいろやろうと思ってるんで。 鑓屋、水俣に来い! 一緒にやろう。
あと、「長くやっててよかった」とか言って、マウントとるみたいに聞こえてたらすみませんでした。その後に「鑓屋さんはまだ何年ですけど」って松村さんが言われて、「あ、やっちゃった」って。すごい圧かけたかもしれない。
ごめんなさい。
鑓屋
それに関しては本当、ただただ尊敬の念とかいうと、また先輩がっていう話ですけど、長く続けられるってすごいことだなと思って。
永野
いや、とんでもないです。
松村
鑓屋さん、長島での今後の活動というか、予定されてることがあったらここでぜひ。
鑓屋
長島愛生園は2030年、まだもうちょっと先なんですけど、開園して100年になるんです。 そこに向けていろんな人に話を聞いたりしたいなって思ってます。
その中でラジオ番組をやってみたいなって思っていて。それもさざなみハウスの取り組みを喋るっていうよりは、私自身がここの人たちと話しててすごく心が落ち着くんですよ。
些細な悩みとかも、「もういいっか」って気持ちになるし、悪口でさえ聞いててなぜか安心するというか。
「いくら歳とっても寂しい時は寂しいんよ」とか、「こうやって愚痴る時間が大事なの」とか。そんな話がすごく楽しくて。
お悩み相談してほしいなと思って。
松村
おお、長島から。
永野
いいですね。相談しちゃおうかな。
鑓屋
お悩みを募集して、どうですか?ってお話を聴くラジオ番組っていいなと思って。
これは見切り発車でも、やってみようと思って。
永野
パーソナリティですね。すごい。
「鑓屋翔子のさざなみハウス!」聴きたーい。

松村
そろそろ2時間。本当に縁側でおしゃべりしてるような時間でしたけど。
永野
確かに、おしゃべりしてるような時間でしたね。
松村
でも、鑓屋さんが長島にいてくれて、水俣に永野さんがいてくれてよかった、会いに行きたくなったって、みんな思ってるんじゃないかなと。
永野
水俣にもいろんな人たちがいるので、会いに来てください。
きっとさざなみハウスの周りにも、濃い人たちがいるだろうから、私もその人たちとの出会いも楽しみに行きたいです。
松村
では、鑓屋翔子さんと永野三智さん、今日は楽しいお話をありがとうございました。
ご参加くださったみなさまも、どうもありがとうございました。

【おわります】






