1983年熊本県水俣生まれ。
中学卒業後に水俣を離れるが、書道の恩師・溝口秋生さんの水俣病裁判と出会い、2007年水俣に戻る。
2008年より、水俣病センター相思社職員。水俣病患者相談窓口や相思社の運営する水俣病歴史考証館の解説、機関紙「ごんずい」の編集などを担当。
単著に患者と向き合う日々の思いをつづった『みな、やっとの思いで坂をのぼる 水俣病患者相談のいま』(ころから/2018年)がある。
人や場所の記憶を受け取り伝える方法はひとつではないし、
特定の誰かが伝えていく必要もない。
受け取ったその人が自身の内面の世界に波紋を広げていった先に「継承」という行為が現れてくるのではないでしょうか。
これまで大きな主語で語ってこられた数々のこと、小さく小さく、個々の物語にしたときに見えてくる何かがあるのかもしれません。
長島から生まれる様々な対話によって、自分と異なる他者に触れる。
まだ知らない私自身を発見する。尊重という行為を知る。
そうして、新しい世界へ橋が架かっていくと私たちは信じています。
大切なことは、目に見えるとは限らないし、
聴こえてくるものでもないかもしれない。
はたまた、自分の輪郭さえ失うほどの闇の中で、
見つかるかもしれない。
国立療養所 長島愛生園は2030年に100周年を迎えます。
幾重にも重なった歴史を自身の身体を使って紐解き、
足元深く、内面にある新しい感覚を呼び覚ます。
ひらかれた長島から心に橋を架け渡します。

(一財)水俣病センター相思社
永野三智
NAGANO Michi

dialogue

喫茶さざなみハウス
鑓屋翔子
YARIYA Syoko

岡山大学文学部准教授
松村圭一郎
MATSUMURA Keiichiro
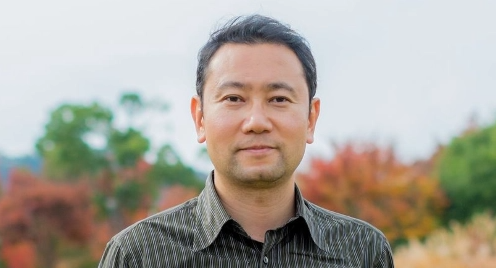
水俣病センター相思社
永野三智
NAGANO Michi

喫茶さざなみハウス
鑓屋翔子
YARIYA Shoko

1988年大阪市生まれ岡山育ち。
大学を卒業してUターン、地方で暮らすことを模索し、働きながら近所の空き家を改修したり、中間支援のNPOで県内の地域に出向いたり、ゲストハウス複合施設での勤務を経て、2019年7月より長島愛生園内で喫茶さざなみハウスをスタート。
喫茶営業のかたわらで、入所者の方の暮らしや療養所の歴史を記録し、島の外にいる人たちに向けて発信しています。
岡山大学文学部准教授
松村 圭一郎
MATSUMURA Keiichiro

1975年熊本生まれ。
岡山大学文学部准教授。
専門は文化人類学。
所有と分配、海外出稼ぎ、市場と国家の関係などについて研究。
著書に『うしろめたさの人類学』(ミシマ社、第72回毎日出版文化賞特別賞)、
『はみだしの人類学』(NHK出版)、
『これからの大学』(春秋社)、
『くらしのアナキズム』(ミシマ社)など、
共編著に『文化人類学の思考法』(世界思想社)、『働くことの人類学』(黒鳥社)。
逆境を乗り越えて、光を探す

松村
水俣にも若い人が外から入って来たり、いろんな動きが起きてますが、長島もそういう意味ではいくつも企画が試みられてきたなと。
今思い出したんですけど、『長島アンサンブル』っていう企画は、さざなみハウスができる前からですよね。
音楽祭というか、音楽フェスみたいな。あの企画にも鑓屋さんは関わっていらっしゃった?
鑓屋
愛生園は国立施設なんですけど、『長島アンサンブル』の時は所在地の瀬戸内市が療養所の世界遺産登録に向けて、いろいろ動き出していたところで、当時働いていた岡山市街のお店の法人が愛生園内で音楽イベントをしたのをきっかけに長島との縁ができて。
松村
そうか、そうか。
鑓屋
そうなんです。
でも私はその当時は長島に行くことはあっても、基本的にはお店にいたし、あまり交流がない状態だったんです。
お店を辞めた後に市議会議員さんの選挙の手伝いなんかをしているときに私も愛生園に通う機会が増えて、話を聞いているうちにお店を出すらしいとか、喫茶交流スペースをつくるらしいみたいな。「で、誰がやるんだ?」。
そんな話になってきた時に自然と「はい!」みたいな。そういう流れで今ここにいます。
永野
「鑓屋じゃない?」って。すごい。
松村
入所者の数はどんどん減っていて、ハンセン病の療養所を今後どうしていくかという課題もありますよね。
近くの邑久光明園には、特別養護老人ホームができたと聞きました。
そうした外に開いていく動きもあると思うんですけど、長島では『青い鳥楽団』でしたっけ?
かつて療養所内で活動していた音楽グループの楽譜とかを再現してアーティストの方が演奏会をやったりとか、いろんな文化的な活動もなさってますよね。
鑓屋
歴史館にいろんな資料が残っていて、いろいろと勉強をしたんですけど、パッと目に入ってくるのは、ゲートボールの活動だったり、『青い鳥楽団』は目の見えない人たちで結成したハーモニカ楽団で、みなさん手先が不自由だったり、ケガでなくなったりしていたから、不自由な体でも演奏できる楽器っていうのがハーモニカだったんです。
不自由でも吹けるように首にかけられる細工をしたハーモニカを使って。
そういう活動の資料が多く残っています。
2階に上がっていくと、子どもたちが書いた作文が載っていて、それぞれに生み出した表現がとてもすばらしくて、胸に刺さるというか、深く心に残るようなものなんです。
やっぱりそれぞれが抱える闇というか、そういうところに惹きつけられて自然とフォーカスされていて。
療養所に不本意ながら連れて来られて、家族と離れた中での集団生活があり、想像するにすごく大変だったんだろうなって思うんです。
けれどその生活の中で逆境を乗り越えて、自分たちの楽しいことを見つけたり、生きがいになるようなことを探求したり、自ら光を探し出しているというか。
そういう強さに私たちも惹かれるし、きっとここに来るアーティストの方たちもそういう部分を肌で感じられて、あんなふうに再現をしてみようと動かされるんじゃないかなと思います。
【つづきます】







