1983年熊本県水俣生まれ。
中学卒業後に水俣を離れるが、書道の恩師・溝口秋生さんの水俣病裁判と出会い、2007年水俣に戻る。
2008年より、水俣病センター相思社職員。水俣病患者相談窓口や相思社の運営する水俣病歴史考証館の解説、機関紙「ごんずい」の編集などを担当。
単著に患者と向き合う日々の思いをつづった『みな、やっとの思いで坂をのぼる 水俣病患者相談のいま』(ころから/2018年)がある。
人や場所の記憶を受け取り伝える方法はひとつではないし、
特定の誰かが伝えていく必要もない。
受け取ったその人が自身の内面の世界に波紋を広げていった先に「継承」という行為が現れてくるのではないでしょうか。
これまで大きな主語で語ってこられた数々のこと、小さく小さく、個々の物語にしたときに見えてくる何かがあるのかもしれません。
長島から生まれる様々な対話によって、自分と異なる他者に触れる。
まだ知らない私自身を発見する。尊重という行為を知る。
そうして、新しい世界へ橋が架かっていくと私たちは信じています。
大切なことは、目に見えるとは限らないし、
聴こえてくるものでもないかもしれない。
はたまた、自分の輪郭さえ失うほどの闇の中で、
見つかるかもしれない。
国立療養所 長島愛生園は2030年に100周年を迎えます。
幾重にも重なった歴史を自身の身体を使って紐解き、
足元深く、内面にある新しい感覚を呼び覚ます。
ひらかれた長島から心に橋を架け渡します。

(一財)水俣病センター相思社
永野三智
NAGANO Michi

dialogue

喫茶さざなみハウス
鑓屋翔子
YARIYA Syoko

岡山大学文学部准教授
松村圭一郎
MATSUMURA Keiichiro
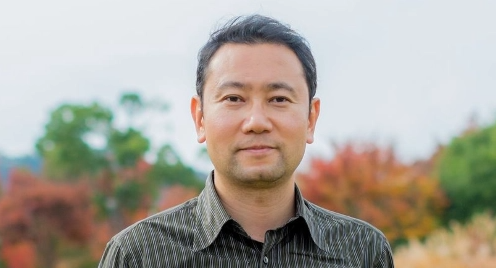
水俣病センター相思社
永野三智
NAGANO Michi

喫茶さざなみハウス
鑓屋翔子
YARIYA Shoko

1988年大阪市生まれ岡山育ち。
大学を卒業してUターン、地方で暮らすことを模索し、働きながら近所の空き家を改修したり、中間支援のNPOで県内の地域に出向いたり、ゲストハウス複合施設での勤務を経て、2019年7月より長島愛生園内で喫茶さざなみハウスをスタート。
喫茶営業のかたわらで、入所者の方の暮らしや療養所の歴史を記録し、島の外にいる人たちに向けて発信しています。
岡山大学文学部准教授
松村 圭一郎
MATSUMURA Keiichiro

1975年熊本生まれ。
岡山大学文学部准教授。
専門は文化人類学。
所有と分配、海外出稼ぎ、市場と国家の関係などについて研究。
著書に『うしろめたさの人類学』(ミシマ社、第72回毎日出版文化賞特別賞)、
『はみだしの人類学』(NHK出版)、
『これからの大学』(春秋社)、
『くらしのアナキズム』(ミシマ社)など、
共編著に『文化人類学の思考法』(世界思想社)、『働くことの人類学』(黒鳥社)。
巻き込まれて、
共にある存在

松村
永野さんはどちらかというと、問題のど真ん中で生まれ育ったっていうか、
小さい時から身近に胎児性水俣病の患者さんとかもいるような環境で育ってこられたわけですよね。
ある意味最初から当事者と隣り合わせというか、でもだからこその苦悩もあると思います。
先ほど「支援者なのか?」っていう言葉が鑓屋さんから出てきましたけど、
永野さんは自分のこの問題に対する関わり方みたいなことをどういうふうに考えていらっしゃいますか?
永野
最近すごく楽しいです。
楽しくなってきてよかったなと思ってます。
前はもう「なんでこんなに苦しいの?」「こんなに苦しくていいんだろうか」って思ってたんですけど、
最近は苦しみはもちろんありながら、水俣病事件の歴史を紐解いていくのが楽しい。
いろんな人たちのお話を聞く中でやっと分かることや、資料を見て、点だらけだったものが線になっていくのが感じられる。
「子どもの頃のあれってこういうことだった」ってことの種明かし。
「この人は背景にこういうことがあったから、この言動につながるのか」とか。
たった今水俣病に関わり始めた人たちって結構苦しい時期なんじゃないかなと思うんですが、
その時間が大切だと思います。
「その苦しみの時間をどうか満喫してくれ」「今しかないんだよ、それは」と。
羨ましいなって思います。
先ほど話をしていた妹さんを水俣病で亡くした女性なんですけど、今年の妹さんのお命日に、
今年は私が見てないところでお参りなさっていて、線香の香りで気がついたんです。
相思社には仏壇があって、その彼女の妹さんをはじめ、
水俣病で亡くなった方たちのお位牌をお預かりしてるんです。
それでよくいらっしゃるんですね。
今年は「ビナを取りに行くよ」とか、「ツワンコを」「ノビルがね」っていうアプローチがあって。
ツワンコの皮を剥いて調理をするのって、すごく手間暇がかかるんです。
手間暇がかかるんですけど、そのおかげで彼女が妹さんの話をして悲しむということが一切なかったんですよ。
とにかくツワをむくことに精一杯みたいな時間で。
それで、私はここでどういう存在なんだろうなと考えたら、
「共にある」という、その一点でいいんじゃないかなって改めて思ったところでした。
支援者だとか、水俣病を学び伝える者だとか、そういうことも大切なんですけど、
まずは「ここで、ここの人たちと共にある」っていうことがとっても大切なんじゃないかと思ったのと、
でもやっぱり伝えることとか、考えることは止めたくなくって。
それは私自身がすごく楽になることだからだとも思うんですよね。
“継承”とか、“風化をさせない”っていうことが、このトークイベントのテーマのひとつだと思うんですけど、
水俣では今、水俣病が漂白されようとしている。
というか、漂白されつつあるんですね。
水俣にはチッソっていう大きな企業の工場があって、その工場が水俣病の原因を生んだんですよね。
その工場は今でもとても大きな影響力を持っているんです。
従業員がチッソに声をあげたのが今から60年ぐらい前なんですけど。
水俣病の患者運動とは全く別のところで声をあげて、従業員たちがチッソに抵抗をするっていう、政治の構図ができたんです。
「チッソという企業対チッソに声をあげる従業員と患者」みたいな。
その構図は段々とチッソの力が強まって、チッソの従業員の力が弱まって、
対等ではなくなってきたっていうのが今の状況だと思うんです。
2018年以降は本当にその状況が強くなって、例えば、
水俣病関係者が行う事業の予算がゼロになるとか、福祉の予算が大幅に削減されるとか。
「『水俣病』や『公害』の文字を消していこう」みたいな流れも強くなりました。
ジョニー・デップが、ユージン・スミスという
水俣病を撮った写真家を演じた映画『MINAMATA』が公開されたんです。
水俣で先行上映会をやろうというので、実行委員の人たちが水俣市に後援を依頼しました。
水俣市の後援をもらえたら費用やいろいろなメリットがある。
いま市報に掲載できるイベントって、水俣市が後援してるもの以外ダメだということもあって。

松村
えーッ!?
永野
民主的な社会が崩壊してきてるなって思うんですけど、その中で市長が後援しない理由として、
「忘れたい人たちがいる」「その人たちに寄り添いたい」と言ったんですよね。
先日、私がファンの作家で血友病患者の大西赤人さんっていう方と話をしてて、
その時に私が使った言葉が“漂白”されているっていう言葉だったんですが、
それを受けての大西さんの答えになるほどなと思って、これは使おうと思った。
風化っていうのは山が段々削れて小さくなっていったりとか、川が削れて形が変わっていったりとか。
例えば30年前の野球の試合で、「俺たちが6回もエラーをして負けた」っていうのが、30年後の同窓会で、
「いや俺たち、あの時惜しかったけどな」っていう話に変わってるみたいな。
時間の経過による風化って仕方ないけれども、市長の言葉は、なんていうか、
「意図的に風化させられている」と。
私、水俣病の事件のことは、水俣の人たちにこそ語り継いでもらいたいって思うんですよね。
けど、忘れたい人たちがいるのも事実で、それはもう本当に悲惨な事件が起きたし、
町が分断されてしまってとか、差別もひどかったしとか、今でもその悲惨さをずっとひきずっていたりだとか、
語れないとか、忘れたいっていうことがあるっていうことは、それも理解したい。
だからこそ、今水俣の外からやってきて語ろうとする人たちの存在がとても大きいなと思うんですよね。
相思社の職員は半分以上外からやってきた人たちなんです。
もう私たち、水俣病オタクですよ。
「水俣病大好き!」「こういうことあったらしいっすよ」「えー、そうなの?そんなの初めて知った」みたいな。
相思社には朝ミーティングを30分、それとお茶飲み休憩が一日二回あるんですよ。
前日の報告をして、そこで困ったこととかを語り合うんですけど、10時と15時にお茶の時間があって、
その時間に自分が最近知ってびっくりしたこととかを披露しあうわけですよ。
私はその外からやってきた職員たちの存在に救われてきた。
水俣病がタブーではない、傷ついていない、それをリアルに知らない人たちの存在に。
それって多分大切で、当事者ではない者が何ができるかっていう可能性がそこにあると思うんですよね。
その当時を生きていないからこそ、当時を生きた人たちの話を聞くことができる。
それが今、鑓屋さんがやっていらっしゃることなんだろうなと思うんです。
相手が知らないからこそ自分のペースで語れる、自分が傷つくかもしれないことは語らないでいさせてくれる、
そういう安心感があったり。
私は相思社にいて本当にラッキーだなと思います。
水俣病に関わりながら、外からの人たちが寄せてくれる安心感みたいなものも得られ、
かつ、患者の人たちや地域の人たちとの関わりのなかで、水俣病のリアルみたいなものも感じつつ。
水俣病に関わった以上はみんなある意味当事者だと思います。
ここに来る患者の人たちの話を聞いた時点で私は当事者になってしまうし、
その人たちと関係をもってしまうし、多分このトークイベントで話を聞いたみなさんももう当事者になってしまう。
この話を聞いた人の口から今日のことが語られる。で、語った瞬間にもう当事者になっちゃう。
「もう語らずにはいられない!」みたいになるといいな。
「ハンセン病を語らずにはいられない!」「今日鑓屋っていう人の話聞いて、こう思ったんだよね。
それでもうちょっと深められたらいいなと思うから、鑓屋に明日電話してみる」っていうことになって、
鑓屋がしめしめ。ってなるといいなと思って。

松村
その巻き込まれていくっていうのは、たしかにそうだなぁと思って。
私もさざなみハウスに子どもを連れて家族で一度訪ねたんですけど、
小学生の子どもには別に何の説明もせず、「パフェ食べれるよ」とか言って連れて行ったんです。
後ろの席に入所者の女性の方がいらっしゃって、「私は10歳くらいの時この島に連れて来られたんよ」
みたいな話をなさってるんですよね。
それがなんとなく娘の耳にも入って、ちょうどうちの上の娘が10歳くらいだったんですけど、帰りの車の中で「なんであのおばあさん、10歳で連れて来られたの?」
って質問してきて、しめしめみたいな。
「この島はね、実はこういう病気で隔離されるっていう歴史があったんだよ」みたいなのって、社会科見学で「ハンセン病のことを勉強しにいきましょう」とは、
違うかたちで自然と当事者に触れて、声が後ろから聞こえてくるみたいな。
そういう場所って、これまでなかったんじゃないかと。
そこがさざなみハウスのすごいところだと思ったんです。
【つづきます】







